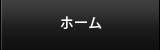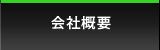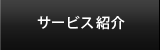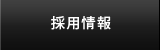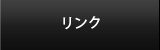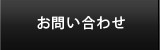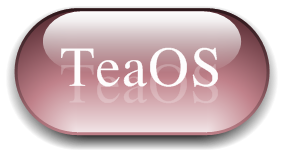会社概要
| 概要 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社ティー・パートナーズ |
| 目的 |
|
| 本店 | 千葉県我孫子市並木7丁目3番19号 |
| 代表 | 野間口 徹 |
| 電話番号 | 04-7183-2576 |
| FAX | 04-7183-2576 |
| メール | [email protected] |
トップ・メッセージ

世の中には複数のものを組み合わせることで、相乗効果で価値が急激に増すもの、量に比例して価値が増すもの、連携が困難になり価値(効率)が急激に減るものがあると思います。そのため、如何に連携の困難性を排除し、如何に相乗効果で新たな価値を引き出すのか、それが大きな仕事を成功させるために重要なポイントになるのかと思います。
TeaOSはそういったポイントを満たすための基盤技術として開発していますが、このTeaOSを活用して多くの人が成功してくれることを切に願っています。